はじめに
CX開発グループ・アプリ開発グループでエンジニアリングマネージャー(EM)をしている仲見川です。昨年9月よりCX開発グループのEMを担当することになり半年がたちました。プレイングマネージャーと、ノンプレイングマネージャーの両方を経験し、N=1の小さなサンプルではありますが得られた気づきを共有したいと思います。
マネジメントスタイルの概要
ノンプレイングマネージャーとは?
ノンプレイングマネージャーは、コードを書く・レビューするなどの開発実務を持たず、チームや組織の成果を最大化するためにマネジメント業務にフルコミットする役割です。人材育成、組織設計、採用、ステークホルダー調整など中長期テーマを中心に動きます。「The マネジメント」というイメージが強い印象です。
プレイングマネージャーとは?
プレイングマネージャーは、マネジメント業務を担いつつ、自らコードを書き・レビューし、設計や障害対応など開発実務にも積極的に参加する役割です。現場の技術的コンテキストを保持しながら、短期的な課題解決や意思決定のスピードアップを図れる点が特徴です。いわゆる開発チームのリーダーの役割に近い印象でしょうか。
ノンプレイング体制での学び
主なタスク
- 事業部側との橋渡し(プロダクトオーナー・CSとの調整)
- 2〜3年先を見据えた組織目標や技術ロードマップの策定
- 採用活動(母集団形成〜面接〜オファー)
取り組んだタイミング
- 期初の目標設定期間
良かった点(Pros)
- 組織の長期目標や技術的展望について、腰を据えて思考・検討する時間が取れた
- 目標を軸としてチームメンバーと深い1on1を実施できた
- 採用の認知形成など“種まき”系の施策をじっくり進められた
苦労した点(Cons)
- スクラムチームが大きいPJに集中していると、小粒タスク(改善、影響のあまりない不具合)が滞留しやすい
- 手を動かさない分、技術トレンド習得の機会を意識的に作らないと取り残されがち
- “成果の見えにくさ”から自己効力感を感じにくい
プレイング体制での学び
主なタスク
- スクラムチーム内の一部開発タスクを自ら担当(30分〜1時間で完了する細粒度タスク中心)
- 橋渡し業務をチームメンバーに委譲しつつフォロー
- 採用活動は継続しつつも認知形成については縮小気味
取り組んだタイミング
- リネットの繁忙期準備〜繁忙期(新機能リリース前の追い込みなど)
良かった点(Pros)
- 小粒タスクが着実に消化され、事業・事業部門の細かな要望にスピーディーに対応できた
- チームとしても頭の片隅にあるやらなければ、と言うタスクを消化できた
- 短期的な成果が得られ自己効力感が感じられる
苦労した点(Cons)
- 中長期テーマ(組織設計、採用など)に割ける時間が減少
- コンテキストスイッチが激しく、意思決定の質が下がりやすい
- “任せる”機会が減り、メンバーの成長機会を奪うリスク
- 機能リリースなど成果を感じられてしまうため本来取り組むべき組織の長期的成長から目が逸れてしまう
行き来して見えたこと
| 視点 | ノンプレイングに寄ったとき | プレイングに寄ったとき |
|---|---|---|
| 考える時間軸 | 中長期(半年〜数年) | 短期(数日〜数週間) |
| 成果の粒度 | 組織設計・採用・文化醸成 | 機能開発・バグ修正 |
| リスク | 運用負債・現場感の薄まり | 戦略的課題の後回し |
| キーメトリクス | Engagement, Retention, Hiring speed | Lead time, Cycle time, Bug count |
両者はトレードオフの関係に見えますが、実際には振り子のように適宜振れることでバランスを取れると感じています。 足下ではプレイングは短期的な成果が得やすく、事業貢献出来ているように思える(実際に出来ているのは事実)ためついついプレイングに時間を割いてしまいがちでした。
まとめと今後の挑戦
- ノンプレイング: 組織の未来を描く、仕組みを作る、育成にコミット
- プレイング: 現場を加速させる、小さな顧客価値を積み上げる
今回は繁忙期で小粒のタスクがあふれている状態を脱するためにプレイングスタイルを取ったのですが、結果的に両方のスタイルについて理解が深まり。 どちらにもPros・Consがあり、両輪としてバランスを取っていくのが今のチームでは良さそうだと感じました。
今後は、ある程度行き来することでよりよいマネジメントが出来るようにチャレンジしてみようと考えています。
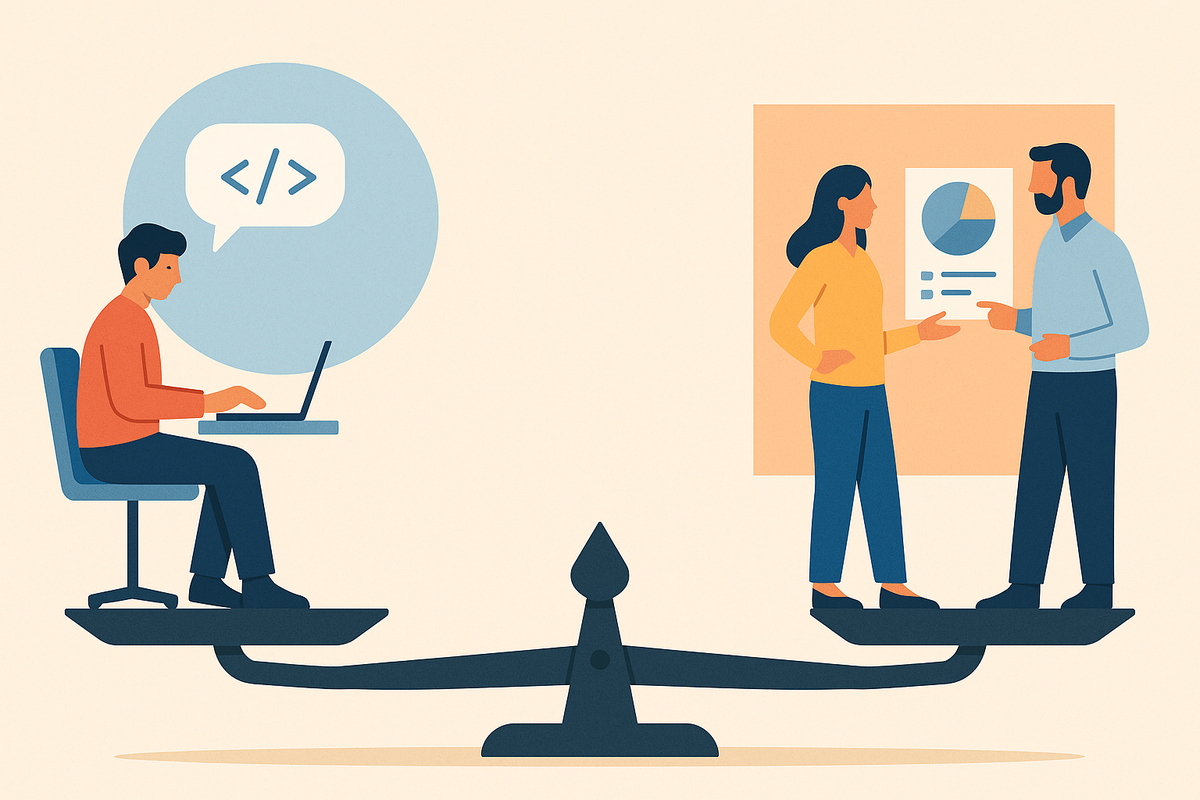
そのために、
- 自身のスキルマップを定義し、意識的にモード切替を行う
- メンバーへ権限移譲し、プレイング時間を創出できる仕組み化
- 組織や事業の状態に応じて適切な割合を見つけ、中長期の戦略と短期的な成果の両立
などに取り組み、より再現性と安定感のあるマネジメントスタイルを探っていきたいと思います。